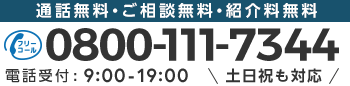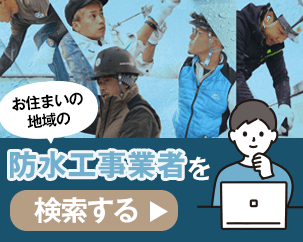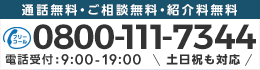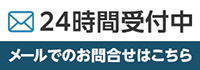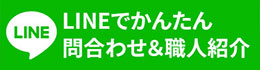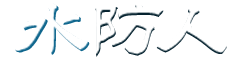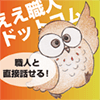防水工事はなぜ高い?費用の内訳と費用を抑えるポイント
2025/07/11

「防水工事の見積もりが思ったより高い…」「どうしてこんなに費用がかかるの?」
そんな疑問を持ったことはありませんか?
屋上やベランダ、外壁の防水工事は建物を雨漏りや劣化から守るために必要不可欠ですが、実際に見積もりを取るとその金額に驚く方も少なくありません。この記事では、防水工事が高額になる理由や費用の内訳、賢く費用を抑えるポイントまで分かりやすく解説します。
防水工事の必要性と失敗した場合の危険性
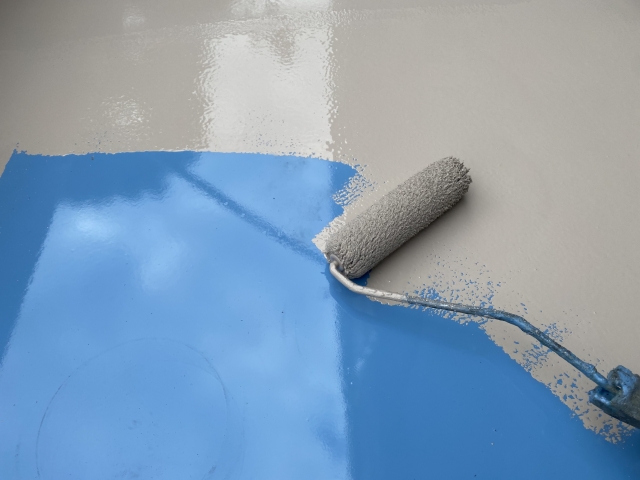
防水工事は、住まいの寿命を左右する“建物メンテナンスの要”とも言える重要な工事です。
日本は梅雨や台風、集中豪雨などの気候的特徴があり、雨水や湿気が建物内部へ侵入しやすい環境にあります。そのため、屋上やベランダ、外壁といった「雨が直接あたる部分」の防水性をしっかり確保することが、長く安心して暮らすために欠かせません。
防水工事がしっかり施されていれば、屋上やベランダ、外壁からの雨水浸入を防ぎ、建物内部の鉄骨や木材の腐食、断熱材や下地のカビ発生、クロスや床の劣化などを未然に防げます。
反対に、防水工事を先送りしたり、費用優先で「とにかく安い業者」を選ぶと、後々次のような深刻なトラブルに直結してしまうリスクがあります。
防水工事を怠った場合の具体的なトラブル
防水工事を怠ると、まず屋上やベランダから雨漏りが始まります。これは早期発見が重要で、最初は小さなシミや水滴程度でも、そのまま放置すると天井、壁の内部、さらには床下にまで水が広がり、お住まいの快適さを損なってしまいます。
また、一度でも雨水が建物内部に侵入すると、鉄骨が錆びたり、木材が腐ったり、断熱材にカビが生えたりと、建物の骨組み自体にダメージが広がっていきます。カビやシロアリが発生すると、ご家族の健康被害や建物のさらなる劣化につながることも。
小さな防水補修を先送りにして雨漏りや腐食が進行すると、結果的に「屋根や壁の全面的な張り替え」「下地からのやり直し」といった大規模な工事が必要になり、費用も大幅に増えてしまいます。
さらに、こうした「雨漏り歴」のある建物は資産価値が低下し、将来売却される際にも大きな不利益となるのです。
“安かろう悪かろう”が特に危険な理由
防水工事は、材料選び・下地処理・施工技術など、すべてが仕上がりや耐久性に直結します。「見積もりが安いから」といって安易に業者を選んでしまうと
・材料や工程の省略による手抜き工事
・下地の不良や劣化を見逃したままの施工
・保証やアフターサービスがない
・専門知識や技術の不足による施工ミス
といったリスクが高まり、「数年で剥がれや雨漏りが再発」「何度も修理を繰り返す」「最終的に高額な再工事が必要」といった事例は後を絶ちません。
特に、建物の防水は“表面だけきれいでも、内部の防水層が不十分”という見た目では判断できない不具合が多いため、しっかりした業者選びと定期的な点検・メンテナンスが不可欠です。
防水工事の費用が高くなる理由
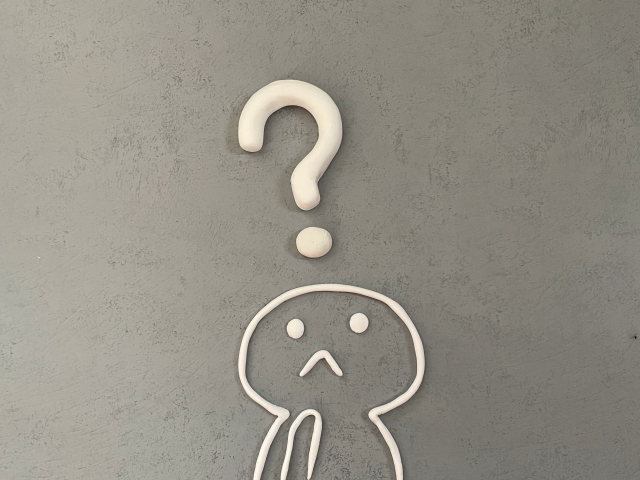
専門性の高い技術・資格が必要
防水工事は「ただ塗るだけ」「貼るだけ」ではありません。
下地の状態や建物ごとの条件を正しく判断し、国家資格を持った職人や、専門的な技術・知識が必須。
また、施工後の保証や万が一のトラブル時の対応まで責任を持って行う体制が求められるため、一定の人件費・管理費がかかります。
高品質な材料費
防水材は安価なものから高機能・高耐久なものまで幅広くあります。
建物を長く守るには適切な材料選びとメーカー保証が重要。
グレードの高い材料ほどコストは上がりますが、その分長期的なメンテナンス費用を抑えることができます。
手間と工程の多さ
・下地処理(劣化やひび割れの補修、洗浄、プライマー塗布など工程が多い)
・複数回の塗布・乾燥(ウレタン防水などは2~3回塗り重ね、乾燥を十分に待つ必要あり)
・養生作業(周囲を汚さないように養生も徹底)
また、天候や気温によって工事が延期・中断されることもあり、スムーズに進まない場合もあります。
足場や仮設の設置費用
戸建て・マンション問わず、足場設置は安全と品質維持のため必須。
足場費用の相場は10~30万円程度。
仮設トイレや養生シートなど、現場環境を整えるための経費もかかります。
諸経費・現場管理費
・職人の人件費・交通費
・保険料(賠償責任保険など)
・施工管理や事務処理のコスト
安心・安全な工事のために、こうした目に見えないコストも含まれていることを理解しましょう。
防水工事の費用内訳(相場と内訳例)
防水工事の費用は、「工法」「面積」「下地の状態」「建物の形状」などによって大きく異なります。
・ウレタン防水:4,000~7,000円/㎡
・シート防水(塩ビ・ゴム):5,000~8,000円/㎡
・FRP防水:5,500~9,000円/㎡
・アスファルト防水:6,000~10,000円/㎡
これに加えて…
・足場費用:10~30万円(戸建て2階建て例)
・下地補修・撤去費:数万円~(状態により大きく変動)
・職人の手間賃・管理費:全体の20~30%ほど
・諸経費・運搬・廃材処理:数千円~数万円
【見積もり例】(30㎡の屋上ウレタン防水・足場ありの場合)
| 内訳項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| ウレタン防水工事 | 210,000円 |
| 足場設置 | 150,000円 |
| 下地補修 | 30,000円 |
| 諸経費 | 20,000円 |
| 合計 | 410,000円 |
追加費用が発生しやすいケース
防水工事は、現場ごとに状態や条件が異なるため、最初の見積もり時点では分からなかった追加費用が発生するケースも少なくありません。特に以下のようなケースでは、予算オーバーや想定外の出費につながることがあるので、契約前に“追加費用が発生する可能性”をしっかり確認しておきましょう。
既存防水層の著しい劣化や下地の損傷
工事を開始して初めて、古い防水層の下に深刻なひび割れや腐食、下地コンクリートの剥がれや浮きが見つかる場合があります。このような場合は、下地の補修や古い防水層の撤去作業が追加で必要になり、その分の工事費用や材料費が加算されます。
例
・コンクリートの大きな亀裂や欠損
・下地の浮き・剥がれによる全面撤去
・想定よりも大掛かりな補修が必要になるケース
工事中に予想外の雨漏りや構造不良が発覚
解体・洗浄・下地調査の過程で、目に見えなかった雨漏り箇所や、構造内部の腐食、断熱材の劣化などが新たに判明することがあります。
この場合も、部分的な再補修や新たな材料追加、施工工程の変更などが発生し、追加費用が必要となります。
例
・壁内や天井裏での追加雨漏り
・断熱材や構造体の腐食・カビによる補修追加
天候不良で工事期間が延びる場合
防水工事は雨天や強風、低温・高温など天候の影響を非常に受けやすいのが特徴です。天候不良が続くと工事期間が延長し、その分職人の人件費や交通費、機材レンタル代などのコストが増加することも。
特に足場や仮設設備のレンタル期間が延びると、その費用も追加請求される場合があります。
夜間や休日作業が必要な場合
住民の生活や周辺環境への配慮、または工事スケジュールの関係で、夜間や休日の作業が必要になると、割増料金が適用されるケースがあります。
マンションや店舗、工場など、通常の営業時間外にしか工事ができない現場では、特に注意が必要です。
都市部・離島などの地域差
現場が都市部の中心地や交通の不便なエリア、離島や山間部の場合、資材運搬費や職人の移動・宿泊費が割増しになることがあります。
また、駐車場確保や車両制限による搬入出コストが加算される場合も。
費用を抑えるポイント

防水工事は決して安い買い物ではありませんが、ちょっとした工夫や事前の確認で余計な費用を抑えることが十分可能です。以下のポイントを押さえて、納得できる工事とコストパフォーマンスの両立を目指しましょう。
複数業者の見積もり比較
“相見積もり”は賢い消費者の第一歩です。できれば2~3社以上から見積もりを取りましょう。
このとき大切なのは、単なる総額だけでなく、「どこまでが料金に含まれるか」「使う材料や工法は何か」「保証やアフターサービスはどうか」といった内容まで細かく比較することです。
・「○○一式」ではなく明細が明確な見積もりを要求
・不明点や不安な項目は納得できるまで質問
・業者の説明力や対応の丁寧さも選定基準に
値段の安さだけでなく、“信頼できるかどうか”も重要な判断材料です。
必要な工事範囲の見極め
「全体的に古いから全部修理しよう」と考えてしまうと、実は必要のない出費が増えてしまうことがあります。
初期段階のひび割れや表面の劣化、排水口まわりだけの問題であれば、部分的な補修やトップコートの塗り直しで屋根の寿命を延ばせる可能性が高いのです。ご自身では気づきにくい下地の状態や見落としがちなポイントも、専門家による現地調査で正確に判断できます。
屋根の状態によっては、定期的なメンテナンス(表面のトップコートだけを塗り替えるなど)を行うことで、大規模な工事を先に延ばすことも可能です。
タイミングの工夫
工事費用の中で大きな割合を占めるのが「足場代」です。
この足場は、外壁塗装・屋根塗装・雨樋交換など他のメンテナンス工事とも共通で使えます。
外壁塗装や屋根修理の予定があれば、防水工事と同時に依頼することで「足場費用が1回分」で済みます。
複数業者に依頼する場合も、工事時期を合わせられないか調整を検討しましょう。
補助金や助成金の活用
自治体のリフォーム助成金・省エネ補助金
住宅の防水・耐震・断熱などに対し、各自治体でさまざまな補助金制度が用意されています。
申請には「着工前の事前申請」が必要な場合がほとんどなので、必ず工事前に自治体や業者に最新情報を確認しましょう。
火災保険・雨漏り保険の適用可否
落雷・台風・突風などによる雨漏りの場合、保険が適用されることも。被害発生から速やかに業者と相談し、写真や診断書など証拠も準備しましょう。
追加費用が発生しないための事前確認

工事開始後に「想定外の追加料金が発生した…」というトラブルはよく耳にします。
こうしたリスクを避けるためには、
現場調査を徹底してもらう
屋上やベランダの下地までしっかり確認してもらい、見積もりの精度を高めてもらう
見積もり内容を細かく確認
「下地補修がどこまで含まれるのか」「足場や養生費は別途か」など、詳細を業者に確認する
追加費用がかかる条件の明記
「下地補修〇㎡まで含む、それ以上は別途」など、追加工事の基準や単価をあらかじめ見積書や契約書に記載してもらう
疑問点や納得できない点は、“契約前”にクリアにしておくことが、後悔しないための鉄則です。
「安さ」だけで選ぶリスクと注意点

防水工事は一見すると「どこに頼んでも同じ」と思われがちですが、実際には施工品質やアフターサービスに大きな差が出やすい分野です。見積もりの総額だけで決めてしまうと、思わぬトラブルや後悔につながることも多くあります。
手抜き工事や品質低下のリスク
極端に安い業者の場合、材料費や人件費を削るために、安価な材料を使ったり、本来必要な下地処理や工程を省略する“手抜き工事”が行われがちです。
こうした工事は最初はきれいに見えても、数年で防水層が剥がれる・ひび割れる・雨漏りが再発するなどのトラブルが非常に多く、「またやり直し工事」「結果的に費用が倍以上かかる」ケースも珍しくありません。
保証やアフターサービスの欠如
保証書が出ない、工事後のアフターサービスがない業者も少なくありません。
仮にトラブルが起きても「連絡がつかない」「保証内容があいまい」では泣き寝入りするしかありません。
安心して暮らし続けるには、きちんとした保証内容・アフター体制が整った業者を選ぶことが大切です。
見積もりの「一式」表記や不透明な業者には要注意
・明細がなく「工事一式」「材料一式」としか書かれていない
・追加費用やオプションの説明がない
・質問への説明が曖昧
こうした業者は、後から高額な追加費用を請求されたり、実際には必要な工程が行われていないことも。
価格だけでなく、「内訳の透明性」「対応の誠実さ」を見極めることが失敗を防ぐポイントです。
よくある失敗例
・安さだけで業者を決めて、1年以内に雨漏りが再発した
・保証をつけていなかったため、再工事費用が全額自己負担になった
・下地補修や養生など必要な工程を省かれ、施工不良が発覚した
賢い業者選びのポイント
屋根工事の業者選びでは、まず複数の業者から見積もりをもらい、価格と内容をじっくり比較してみましょう。わからない点は遠慮なく質問してください。
大切なのは「安さ」ではなく、信頼できる実績や口コミ、しっかりした保証内容です。
また、工事の内容や進め方をわかりやすく説明してくれて、工事後のサポート体制が整っている業者を選ぶことをお勧めします。
まとめ
防水工事は確かに初期費用がかかりますが、雨漏りを予防し、建物の価値を守り、長い目で見るとコスト削減につながる大切な投資なのです。費用の内訳をきちんと理解して、納得した上で工事を依頼することが、後々の満足につながります。
また、分からないことは遠慮なく業者に質問し、複数の会社から見積もりを取って比較検討することをお勧めします。お悩みの際は【水防人】の無料相談・業者紹介サービスもぜひご活用ください。大切なお住まいを守るために、賢い選択で満足のいく防水工事を実現しましょう。