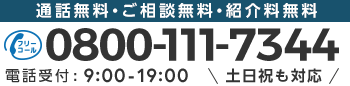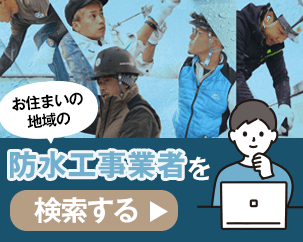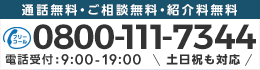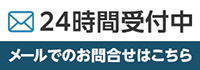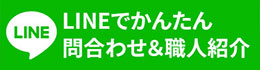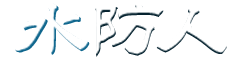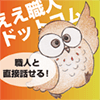雨漏りが再発する原因は?正しい防水工法を選ぶポイントとは
2025/10/07
「前に補修してもらったはずなのに、また雨漏り…」
雨漏りは一度直しても、再発に悩まされる方がとても多いのが現実です。この記事では、なぜ雨漏りが繰り返されるのか、その本当の原因や、失敗しない防水工法の選び方を解説します。
再発リスクを減らすための対策や、信頼できる業者の選び方まで、迷いがちな方にも分かりやすくまとめました。
最後までお読みいただければ、ご自宅の「本当に安心できる防水対策」がきっと見つかるはずです。
雨漏りが「再発」する典型的な例

局所補修の限界と見えない経路
雨漏りは、見えている箇所を一時的にコーキングや板金で補修しただけでは根本解決にならない場合が多いです。建物内部には「水の通り道」が複雑に存在し、表面だけの処置だと水が別の経路を探して浸入し、数ヶ月~数年後にまた同じ場所や別の場所で症状が現れることがあります。
とくに屋根やベランダ、サッシまわりなどは構造が複雑で「見た目の症状」と「本当の原因」が一致しないケースが少なくありません。
下地・構造体まで劣化が進行している場合
表面だけでなく、屋根や外壁の下地、防水シート、木材や金属などの構造体まで水分が回っている場合は、部分的な補修では再発リスクが高くなります。下地の腐食や断熱材のカビ、鉄部のサビなど、建物の見えない部分の劣化が進んでいると、見た目がきれいになってもすぐに雨漏りが再発するのです。
雨漏りが再発しやすい建物・工事の特徴

築年数が古くメンテナンス歴が少ない家
築年数が10年、20年と経過した住宅では、外から見える屋根や外壁だけでなく、その内部の「下地材」や「接合部」まで長年の風雨や紫外線、温度変化の影響を受けています。防水層の寿命は一般的に10~15年程度とされていますが、定期的な点検やメンテナンスを怠っていると、知らないうちに下地材が湿気を吸って腐食したり、金属部分がサビて脆くなっていることも。
こうした深い部分の劣化は、表面を新しい材料で覆うだけでは根本的な解決にはならず、一見きれいに見えても、わずかな隙間や目地、構造の接合部などから再び水が侵入しやすくなります。
特に、築20年を超える住宅や、一度も大規模なリフォームをしていない場合は、“全体の劣化度合いをプロの目でしっかり診断”してもらうことが再発防止の最初のステップです。赤外線カメラや散水調査などを活用し、目に見えない内部まで点検することが重要なのです。
“安さ優先”や下請け任せの工事
「できるだけ費用を抑えたい」という気持ちは自然なことですが、防水工事の場合は“安かろう悪かろう”になりやすい分野です。相場よりも極端に安い見積もりや、内容が不明瞭なまま契約を進めてしまうと、本来必要な下地補修や高耐久の材料選定、十分な施工手順が省略されてしまう危険性があります。
また、大手業者であっても下請け会社に丸投げし、現場管理や技術指導が不十分な場合、経験の浅い作業員による手抜きやミスが発生しやすくなります。
こうした場合、工事後すぐに防水層が剥がれたり、数年以内に再び雨漏りが発生してしまい、「安く済んだつもりが高くついた」と後悔する事例が後を絶ちません。
信頼できる業者を選ぶには、「なぜこの工法・材料を使うのか」「下地の補修範囲はどこまでか」「保証内容は何年か」など、説明が丁寧かつ明確であるかをしっかり見極めましょう。
気候・立地の影響
日本は地域ごとに気候条件が大きく異なり、沿岸部の塩害・台風被害、山間部の積雪、都市部のヒートアイランド現象など、建物が受けるダメージもさまざまです。
特に台風や豪雨の多い地域では、屋根・ベランダ・バルコニーの防水層が受ける負荷が大きくなり、劣化スピードが加速します。また、沿岸部では塩分を含んだ風によって金属部品やシーリング材が早く傷みやすいという特有のリスクも。
さらに、日当たりや風通し、周囲の建物の影響によっても劣化の進み方は変わってきます。
このような地域性・立地条件に合わせて、耐候性や耐久性に優れた材料・工法を選ぶことが長持ちのコツです。地元の気候や環境を熟知した業者に相談し、最適な施工計画を立ててもらうことも大切です。
再発の主な原因ごとにみる「正しい対策」
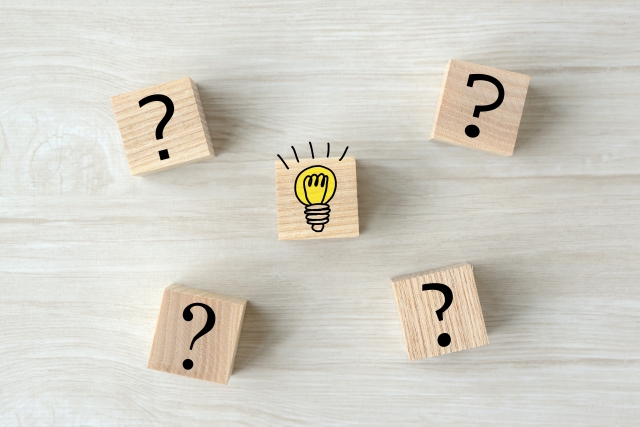
屋根・外壁からの浸水
屋根は、雨水の直撃を受けやすく、特に防水シート(ルーフィング)の劣化や重ね部分のズレ、釘穴の劣化が雨漏りの大きな原因になります。
外壁も、一見すると目立つ劣化がなくても、サイディングやモルタルの目地・継ぎ目のシーリング切れや、細かなクラック(ひび割れ)から水がしみ込みやすいのです。
ここで重要なのは、「表面の補修だけで済ませてしまうと、根本解決にならない」ということ。
本当に再発を防ぐには、下地材の状態や水の経路を徹底的に調べ、場合によっては部分補修ではなく、全面的な改修やルーフィングの貼り替えも検討することが必要です。
また、外壁の防水では「塗装」と「シーリング(コーキング)」の両方がセットで計画されているかをチェックしましょう。
ベランダ・屋上の防水層の劣化
ベランダや屋上は、日差しや雨だけでなく、日常的な歩行や家具の移動などの影響で防水層が傷みやすい部分です。
特にウレタン防水、FRP防水、シート防水など、工法ごとに耐用年数やメンテナンスサイクルが異なるため、「前回の工事がどの工法だったか」「何年前に施工したか」を記録しておくと再発防止の判断材料になります。
現地調査では、ひび割れや膨れ、剥がれ、排水口周りの劣化などを細かく確認し、部分補修で済むのか、全面的な再防水工事が必要かをプロと一緒に見極めましょう。
同時に、立ち上がりや手すり・笠木の防水処理も確認ポイントです。
サッシ・配管まわりからの浸水
窓やサッシ、給排水の配管まわりは、家の中で「水の侵入口」になりやすい場所です。
シーリング材(コーキング)は年数とともに硬化・ひび割れ・隙間ができやすくなります。
特にサッシや配管まわりは、「高耐久タイプのシーリング材(変成シリコン、ポリウレタン系など)」や「二重防水(防水テープ+シーリング)」など、再発防止のための工夫や丁寧な下地補修が大切です。
また、周囲の外壁や床下にまで水が回ることもあるので、必ず下地の状態まで確認し、不安な部分は一緒に補修計画に入れてもらいましょう。
「正しい防水工法」の選び方
施工場所や既存の下地状況を正確に診断
「防水工事」と一口に言っても、現場の下地状態、既存の防水層の種類や劣化度合いによって最適な工法は異なります。
たとえば、表面だけの補修では数年で再発してしまうことも珍しくありません。
必ず現地調査・診断を実施し、赤外線カメラや散水テスト、打診なども活用して、「どこが本当に傷んでいるか」「水の流れがどうなっているか」まで調べてもらいましょう。
各防水工法のメリット・デメリット
・ウレタン防水は施工性が高くコストも抑えやすいですが、厚みや乾燥工程など手間を省略されやすい。
・FRP防水は高耐久で丈夫ですが、紫外線で劣化しやすい部分があり、硬化後の割れにも注意。
・シート防水は工場生産の品質と施工スピードが魅力ですが、複雑な形状には不向き。
・アスファルト防水は耐久力抜群ですが、施工に技術力が必要で、重さもデメリットになることがあります。
業者から「なぜこの工法なのか」「メリットと注意点は何か」を説明してもらい、自分の家に合った工法を納得して選ぶことが再発防止のコツです。
材料のグレード・メーカー名まで確認
「防水工事一式」など、内容がぼんやりした見積もりは後から後悔しやすいです。
使う材料のメーカーや製品名、グレード、保証年数まできちんと説明があるかをチェックしましょう。
安いノーブランドや耐用年数の短い材料を使われてしまうと、数年で再発のリスクが高まります。
施工実績やアフターサービス
工事は一度きりで終わりではありません。過去の施工実績やお客様の口コミ、保証書やアフターサービスの内容も必ず確認しましょう。
工事後に万が一の不具合が発生したとき、「きちんと相談できる業者かどうか」「連絡先や保証書の発行があるか」も重要な判断基準です。
まとめ
雨漏り再発の多くは、応急処置や表面的な工事に頼った結果、根本原因の見逃しに起因します。
「正しい診断」と「適切な防水工法の選定」、そして「信頼できる業者選び」が、安心の住まいと資産価値の維持につながります。
分からないことや業者選びの不安は、ぜひ【水防人】の無料相談サービスもご活用ください。全国の実績豊富な専門業者があなたの大切な住まいをサポートします。
よくある質問・Q&A
Q. 雨漏りが再発した場合、全部やり直しが必要?
A. 範囲や原因によります。部分補修で済むこともありますが、何度も再発する場合や複数箇所に劣化が広がっている場合は、早めの全面改修も検討しましょう。
Q. 工法や材料でどれくらい違う?
A. 耐用年数・費用・メンテナンス性など大きな違いがあります。安さや見た目だけでなく、将来の安心も含めて検討してください。
Q. 補助金や保険は使える?
A. 自治体の住宅リフォーム補助金や自然災害時の火災保険が使える場合もあります。