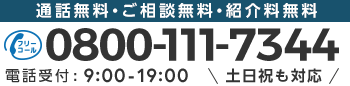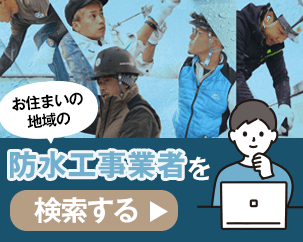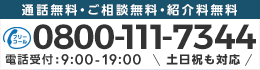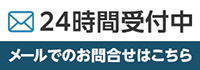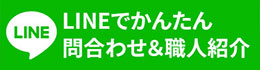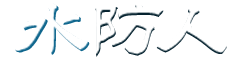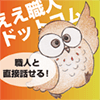屋上緑化と防水工事の関係とは?施工前に知っておきたいポイント
2025/11/06
屋上緑化は、省エネや断熱効果、都市のヒートアイランド対策、景観向上などさまざまなメリットが注目されています。しかし、土や植物、潅水設備を屋上に設置することで、防水層への負担は大きくなります。「屋上緑化の前に防水工事は必要?」「どんな工法が向いているの?」と悩む方も多いでしょう。
この記事では、屋上緑化と防水工事の基本から、失敗しない施工のポイント、専門家に相談すべきケースまで詳しく解説します。
屋上緑化とは

屋上緑化とは、建物の屋上やバルコニーなど、本来コンクリートや防水層で覆われている場所に、芝生や草花、低木、さらには家庭菜園や庭園のような本格的な植栽スペースを設けて、緑の空間をつくる施工のことを指します。
近年では、都市部のビルやマンションの屋上だけでなく、一般住宅や店舗、学校、公共施設などさまざまな建物で屋上緑化が取り入れられるようになりました。特に東京都や大阪市など一部自治体では、屋上緑化を推進するための条例や補助制度が設けられているケースもあり、地球温暖化対策やヒートアイランド現象の緩和策としても注目されています。
また、屋上緑化には「全面緑化(屋根全体を緑化する)」と「部分緑化(歩行スペースやベンチ、植栽スペースを組み合わせる)」のパターンがあり、用途やデザイン、耐荷重の条件によって最適な施工方法が選ばれるのが一般的です。
屋上緑化のメリット

屋上緑化には、単なる見た目の癒しだけでなく、建物や暮らし、都市環境にさまざまなプラス効果があります。
断熱効果・省エネ効果
屋上に土や植物を敷き詰めることで、太陽光が直接コンクリート面に当たらなくなります。そのため夏場の屋内温度上昇を抑えることができ、冷房効率が大幅に向上します。
実際、屋上緑化をした建物では「冷房費が年間で1〜3割削減できた」という事例も珍しくありません。
雨水流出の抑制・浸水被害の軽減
土壌や植栽が“スポンジ”の役割を果たし、雨水の一部を吸収・保持します。
その結果、大雨やゲリラ豪雨の際にも、雨水が一気に下水へ流れ込むのを緩和でき、都市型洪水や浸水被害の軽減にも貢献しています。
騒音低減・遮音効果
屋上緑化は、植物や土壌が“緩衝材”となり、屋外の騒音やビル風を和らげる効果も期待できます。
都市部や幹線道路沿いのマンション・オフィスビルでは、屋上緑化後に「騒音ストレスが大きく減った」という声も多いです。
都市景観の向上・生物多様性の保全
コンクリートやアスファルトで覆われた都市の中に、緑豊かな空間ができることで、景観の美しさや心地よさが向上します。
また、屋上緑化が“小さな生態系”となり、鳥や蝶、ミツバチなど多様な生物が訪れる場にもなるのです。
資産価値の維持・向上
マンションやオフィスビルでは、屋上緑化が建物の付加価値として評価されやすくなります。
定期的な緑化やメンテナンスが行き届いている物件は、入居者の満足度も高まり、将来的な資産価値の維持・向上にも直結するでしょう。
メンタルヘルスやコミュニティ形成にも効果
屋上の緑地空間は、住民やオフィスワーカーのリフレッシュスペースとして活用されることも多いです。
「緑を見ることでストレスが和らぐ」「コミュニティガーデンとして地域交流が活発になる」といった社会的な効果も見逃せません。
屋上緑化で防水層が受ける負荷とは

屋上緑化を行うと、通常の屋上よりも遥かに多様な負荷が防水層にかかるようになります。
まず大きな特徴として、屋上に土壌や植物を載せることで全体の重量が大幅に増す点が挙げられます。
芝生や植木、花壇、家庭菜園など、どのタイプの緑化でも「土」「水分」「根」の三要素は避けて通れません。
これらはすべて、防水層や下地コンクリートに対して“圧力”や“水分滞留”という形で負担をかけ続けることになります。
さらに、植物の根が成長する過程で「防水層を突き破って侵入する」いわゆる根入れ現象が発生する可能性があります。
とくに多年草やツル植物、成長の早い樹種を選んだ場合、年数を経るごとに根が防水層やジョイントの隙間からコンクリート層まで到達するリスクも考えられます。
また、屋上の土壌は雨水や潅水(水やり)によって常に高い水分を含む**ため、防水層が常時湿潤状態に置かれることになります。
この湿気・圧力・根の侵入、三つのストレスが重なれば、通常の屋根やベランダよりも遥かに高いレベルの防水性能が求められるというわけです。
防水層が劣化するとどうなるか?
もし屋上緑化の下にある防水層が劣化していたり、施工不良だった場合には、その被害は想像以上に深刻です。
まず一番のリスクは、屋上からの雨漏りや下階への水漏れ。
一般的な屋根やベランダの雨漏りと違い、屋上緑化の場合は「常に土壌が湿っている」「潅水で定期的に水分が供給される」ため、一度でも防水層に穴や破れができると、短期間で大量の水が建物内部に侵入してしまいます。
こうなると下階の天井や壁、配線・設備まで広範囲に被害が及びやすいだけでなく、カビや腐食、コンクリートの剥離や鉄筋の錆びなど二次被害も深刻です。
さらに、屋上緑化を一旦すべて剥がして防水やり直し…という大規模な工事が必要になることも。
緑化部分の解体・再施工には多額の費用と時間がかかり、住環境や営業への影響も避けられません。
だからこそ、屋上緑化を計画する際には「まず防水層の健全性・耐久性を徹底的にチェックし、必要に応じて防水工事をやり直す」ことが必須のプロセスとなるのです。
この一手間を惜しまないことで、屋上緑化の恩恵を何年も安心して受け続けられる、それが防水工事の最大の意義と言えるでしょう。
屋上緑化に適した防水工法とは?
一般的な屋上防水工法の比較
ウレタン防水、FRP防水、シート防水(塩ビ・ゴム)、アスファルト防水などが使われます。ただし、屋上緑化には「耐根性(根が貫通しにくい)」が必須条件です。
屋上緑化に最適な「耐根仕様」とは
防水層の上に「耐根シート」や耐根性の高い塩ビシート防水を施工するのが主流です。アスファルト防水でも「耐根仕様」の材料があり、植物の根が防水層を破るリスクを最小限にできます。
防水層の“二重構造”と排水計画
多くの屋上緑化では、防水層と「保護層(押さえコンクリートや保護シート)」を組み合わせた二重構造とします。加えて、排水ドレン・雨水流路の設計が重要です。水たまりができない設計が、長持ちのコツなのです。
施工前に知っておくべきポイント
防水層の劣化診断と適切な補修が必須
屋上緑化を始める前に、必ず既存の防水層の状態を専門業者による点検で把握しましょう。
「ひび割れ」「膨れ」「剥がれ」「色ムラ」などの劣化サインが少しでも見られる場合は、そのまま上に緑化を施してはいけません。
表面の補修だけでなく、下地の状態(コンクリートの浮きやクラック、雨染み)まで徹底的に確認し、必要があれば再防水や下地補修を必ず実施してください。
このステップを怠ると、緑化工事後に防水層のトラブルが発生した際、土壌や植物の撤去・再施工が必要になるため、費用も手間も想像以上にかかるリスクがあります。
防水層の診断や補修は、「屋上緑化のための投資」として惜しまないのが賢明です。
工事計画と積載荷重の検討はプロの視点で
屋上緑化は、土壌、植物、排水層、潅水設備などの重量が従来より大きく増すのが特徴です。
「マンションの陸屋根」「商業ビルの屋上」など本来は荷重に強い構造でも、緑化後の合計重量が建物の設計荷重(積載荷重)を超えていないか、必ず事前に構造専門家のアドバイスを受けてください。
特に築年数が経過した建物や、増築・改修の履歴がある物件では、追加補強が必要になることも珍しくありません。
工事の計画段階で「どの場所にどの程度の土を載せるか」「水やり・雨水が溜まったときの最大荷重」を具体的にシミュレーションしておくことが、トラブル防止のカギです。
保証・メンテナンス体制も要チェック
防水工事や屋上緑化は、「やったら終わり」ではありません。
必ず「防水層の保証年数」「緑化部分の保証内容」「定期点検やメンテナンスサービスの有無」を契約時に確認しておきましょう。
また、屋上緑化後は植栽管理やドレン(排水口)清掃、防水層の定期点検も計画的に行う必要があります。
このアフター管理までしっかり対応できる業者や、複数分野をワンストップでフォローできる専門業者の選定が、長期安心の決め手になります。
屋上緑化で発生しやすいトラブルと防止策
雨漏り・水たまりトラブルのリスクと予防法
屋上緑化では、「雨漏り」や「水たまり」が非常に起きやすいトラブルのひとつです。
排水計画が甘かったり、防水層の施工が不十分だったりすると、土壌内に溜まった水分が徐々に防水層を超えて建物内部へ侵入してしまうのです。
また、屋上のドレン(排水口)が土や落ち葉で詰まると、広範囲に水が滞留しやすくなり、雨漏りリスクが一気に高まります。
カビやシミ、下階の天井や壁紙の腐食被害も発生しやすくなり、放置すると大規模な補修が必要になるケースもあるため、注意が必要です。
このようなトラブルを防ぐためには、「排水計画の徹底」と「定期的なドレン清掃」「施工後の点検体制」が不可欠です。
屋上緑化と同時に「排水設備の見直し」や「追加ドレンの設置」も検討しましょう。
植物の根の侵入による防水層破損とその対策
意外と見落とされがちなのが、「植物の根による防水層の破損」です。
一般的な防水材やシートは、植物の根が成長する過程で貫通し、防水層に穴が空く・めくれるといった深刻なトラブルを引き起こすことがあります。
とくに芝生や樹木、根の張りやすい植物を用いる場合は、必ず「耐根仕様」の防水材を採用することが大切です。
また、防水層の上に「耐根シート」や「防根層」を施工することで、根の侵入リスクを大幅に減らすことができます。
施工時には、各層ごとのジョイント部や立ち上がり部分にも十分な配慮が求められます。
「防水層+耐根層」の組み合わせで、長期的な安心を確保してください。
維持管理不足・メンテナンス放置が招くリスク
屋上緑化は施工後の「維持管理」がとても重要です。
植栽の枯死や害虫・雑草の繁殖、排水溝の詰まりなど、定期点検や清掃を怠ると防水層の寿命そのものが短くなってしまいます。
特に「土壌の流出」「コケや藻の繁殖」「根の暴走」などは、数年で大きなダメージに繋がる要因です。
植栽の管理や剪定、排水設備の清掃・点検、防水層の表面チェックなどを半年~1年ごとに必ず実施しましょう。
専門業者による定期点検や、緑化と防水をトータルでサポートするアフター体制を持つ会社を選ぶことが、長持ちする屋上緑化の秘訣です。
施工業者選び・見積もり時のチェックポイント

屋上緑化+防水工事の実績が豊富か
必ず「屋上緑化+防水工事の同時実績があるか」を確認してください。単なる植栽業者や、一般的な防水業者だけでは専門性が足りないこともあります。
工法・材料・保証内容が明記されているか
見積書に、「防水工法名」「耐根仕様かどうか」「材料メーカー名」「保証年数」「メンテナンス体制」などが明記されているかチェックしましょう。
契約内容・工事範囲のすり合わせ
工事前の打ち合わせで、防水層・保護層・排水・緑化範囲・保証内容などを具体的に確認しましょう。疑問や不安は、契約前に必ず解消しておくことが大切です。
まとめ
屋上緑化と防水工事は密接に関わっており、最初の防水層・排水計画・材料選定が成功のカギです。必ず耐根仕様や専門性の高い工法・業者を選び、長期の維持管理計画も忘れずに立てておきましょう。
「自分で判断できない」「見積もりや業者選びが不安」なら、【水防人】の無料紹介サービスをぜひご活用ください。専門スタッフが全国の優良業者を無料でご案内し、工事後のフォローまでしっかりサポートします。
Q&A(よくある質問)
Q. すでに緑化済みの屋上ですが、防水が不安な場合はどうすれば良いでしょうか?
A.
屋上緑化をすでに行っている建物でも、「防水層の劣化が気になる」「雨漏りが心配」というケースは珍しくありません。
まずは防水工事の専門業者による劣化診断・点検を受けることをおすすめします。
必要に応じて、部分的に植栽や土壌を撤去して防水層を確認・補修することも可能です。
防水層のわずかな損傷を放置すると、漏水や構造材の劣化につながることがあります。
定期点検や記録写真の保存など、継続的なメンテナンスを心がけましょう。
Q. 防水工事と屋上緑化、どちらを先に行うべきですか?
A.
一般的には、防水工事を先に行うのが原則です。
既存の防水層が古い・劣化している場合は、緑化前に再防水工事や下地補修を済ませておきましょう。
防水が不十分な状態で緑化を行うと、後からの漏水や補修で「せっかくの緑化を撤去してやり直す」事態になりかねません。
施工順序を決める際は、必ず防水の専門業者に相談し、構造や防根仕様に適した設計順序を確認することが重要です。
Q. 屋上緑化に使える補助金や助成金はありますか?
A.
一部の自治体では、屋上緑化や壁面緑化を対象とした助成金・補助制度が設けられています。
「工事費の一部助成」「設計サポート」「技術相談」などの内容は自治体によって異なり、上限額・申請時期・対象工事も地域ごとに規定されています。
近年は、防水改修や断熱改修とあわせて環境対策として緑化を促進する補助メニューを設ける自治体もあります。
ただし、防水工事自体が助成対象に含まれるかどうかは制度によって異なるため、必ず最新の要項を確認してください。