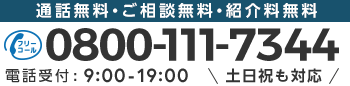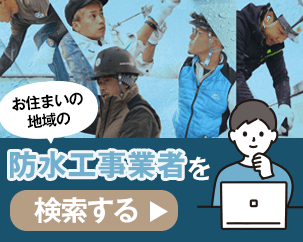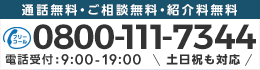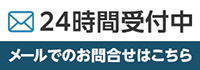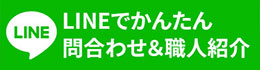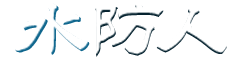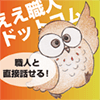防水工事後にやるべきメンテナンスとは?長持ちさせるためのポイントまとめ
2025/08/28
「せっかく高いお金をかけて防水工事をしたのに、すぐ劣化してしまったらどうしよう…」
そんな不安を感じていませんか?防水工事は“やって終わり”ではなく、その後の正しいメンテナンスが耐久性・効果を大きく左右します。
本記事では、防水工事後に長持ちさせるために必要なメンテナンス方法と注意点を、専門家の視点で分かりやすく解説します。
防水工事後のメンテナンスが重要な理由

防水工事は「施工直後が一番強い」わけではありません。
日本の住宅は紫外線、雨風、気温の変化、生活上の衝撃など、さまざまな要因で少しずつ劣化します。
適切なメンテナンスを継続することで、10年→15年以上、防水層の寿命を延ばすことも可能です。
反対にメンテナンスを怠ると、劣化の進行が早まり、せっかくの工事も数年で台無しになってしまうことも珍しくありません。
メンテナンスしない場合のリスク

防水工事をしたからといって「もう安心」と油断してしまうと、気づかないうちに大きなリスクを抱えてしまうことがあります。
防水層は日々の紫外線や雨風、気温差、生活による摩耗などで少しずつ劣化し続けています。適切なメンテナンスを怠った場合、次のような重大な問題を引き起こす可能性があります。
小さなヒビや剥がれから雨水が侵入
たとえ目立たない細かなヒビ割れでも、そこからじわじわと水が入り込みます。
一度水分が侵入すると、表面を補修しただけでは完全に止めるのが難しくなり、雨漏りの原因となります。
下地の腐食、カビ・シロアリの発生
水分が防水層の下まで到達すると、コンクリートや木材、金属の下地が腐食・錆び・カビの温床となり、構造自体の耐久性を著しく損ないます。
また湿気や腐敗臭が広がり、シロアリの繁殖やカビによる健康被害も発生しやすくなります。
軽微な補修が大規模修繕や内装リフォームに発展
本来は数万円程度で済む部分補修でも、放置して被害が拡大すると、床材や壁材の張り替え、断熱材・下地の交換、家具や家電の買い替えなど、数十万〜百万円単位の費用が必要になることも。
とくに「見えない部分(床下・壁内・天井裏)」で水がまわると、表面的な異常が出たときにはすでに深刻なダメージを受けている場合が多いです。
結果的に、資産価値の大幅なダウンや家族の健康被害、さらには住みながらの大規模修繕で生活への大きな負担も生まれてしまいます。
だからこそ、「大丈夫」と思わず、早め早めの点検とセルフケアが欠かせません。
防水工事後にやるべきセルフメンテナンスポイント

日々のちょっとしたお手入れや定期的な点検で、劣化の進行を大きく遅らせることができます。自分でできるセルフメンテナンスの具体的なポイントを紹介します。
定期的な清掃・ゴミ取り
ベランダや屋上の落ち葉・土埃・ゴミは放置せず、こまめに掃除しましょう。水はけが悪くなると、常に湿気がこもり、防水層の弱点を生みやすくなります。とくに排水口やドレンまわりは、落ち葉や泥、ゴミが詰まりやすい場所。
月に1回を目安に掃除を習慣にすると安心です。
排水口やドレン周りも詰まりがないか要チェック。
排水機能が落ちて水たまりができやすくなると、局所的に防水層が膨れたり剥がれたりしやすく、やがて雨漏りの原因に直結します。
異常の早期発見と記録
ヒビ割れ・膨れ・剥がれ・色あせ・水たまりができていないかを目視チェック。
小さな変化も見逃さないよう、ベランダや屋上、外壁などを意識的に眺める習慣をつけましょう。
とくに「色が変わった」「ツヤがなくなった」などの違和感も初期劣化のサインです。
年に2回はスマホで写真を撮り、状態の変化を記録しておくと便利です。
「去年の同じ場所と比べてどうか?」を振り返れるようにしておくと、変化に早く気付けて、専門業者に相談する際も説明がしやすくなります。
雨や台風の後は念入りにチェックしましょう。
強風や大雨でゴミが飛んできたり、外壁・防水層にダメージが出ていることがあります。
天候が落ち着いたら、排水口や床面、壁まわりを一通り点検するのがおすすめです。
水はけ・排水の確認
水が溜まりやすい場所がないか、排水口周りにコケや藻が繁殖していないかを点検。
水たまりや湿気が残る場所は、防水層が弱くなっていたり、下地まで劣化が進んでいるサインのことも。
コケや藻が増えていたら、早めに除去し、状態の変化も記録しておきましょう。
水はけが悪い場合はすぐに専門業者に相談しましょう。
排水口やドレンの詰まり、床面の勾配不良、見えない部分の劣化など、「何かおかしいな」と思った時点で早めにプロに点検依頼をすることが、大規模修繕を未然に防ぐ最大のポイントです。
防水層を長持ちさせる生活のコツ

防水層の寿命を少しでも長く保つためには、日々の生活の中でちょっとした工夫を心がけることも大切です。
重い植木鉢や金属家具などは直置きしない・引きずらない
防水層の上に重い鉢植えや家具を長期間置くと、その部分が凹んだり、傷がついたりして劣化が進みやすくなります。
また、金属脚や車輪が付いた家具などを引きずると、防水層に直接キズが入り、防水性能が低下するリスクも。
ベランダや屋上で鋭利なものを扱う時は床を保護
脚立や大きな工具、DIY作業などで刃物や尖ったものを使う時は、下にゴムマットや厚手のシートを敷いて作業するのが安心です。
定期的に鉢植えや家具の位置を変えて「同じ場所への負荷」を減らす
常に同じ場所に重い物があると、床面の一部だけが早く劣化します。月に1度程度でも場所を少しずらすだけで劣化の予防効果があります。
塩害、鳥害、ペットの糞害が心配な場合は防鳥ネットや定期清掃を
海沿いの地域は塩分が原因で劣化が進みやすく、またカラスやハト、ペットの糞が蓄積すると、防水層を傷める原因になります。
防鳥ネットの設置や、定期的な水洗いで表面を清潔に保つことも長持ちのポイントです。
▷参考記事:自分で設置できる鳩よけネットと失敗しない選び方
専門業者による定期点検とプロメンテナンス

防水層は、たとえ丁寧にセルフメンテナンスしていても、自分では気付きにくい隠れた劣化や内部の異常が進んでいることがあります。
特に屋上やベランダの床下、外壁の内部などは、見た目に問題がなくても内部の下地や接合部で水分がまわり始めていることも珍しくありません。
5年に1回はプロの点検・診断を依頼しましょう。
専門業者は経験と知識に加え、赤外線カメラや散水試験、打診棒などの特殊な道具を使って、目視だけでは分からない劣化や水の侵入ルートまでしっかり調べます。
こうした精密診断で「一見問題なさそうだったけど、早めに発見できて大事に至らず済んだ」というケースも多いです。
プロによる定期点検・補修は、工事保証の条件になっていることも多いため、長く安心して住まいを守る上でも大切です。
また、定期点検の記録や点検報告書は、将来の売却時や万が一のトラブル発生時に「きちんと管理していた証拠」としても役立ちます。
防水工事の保証内容・アフターサービスを再確認
防水工事の効果や安心感は、工事完了後の保証やアフターサービスがしっかりしているかどうかでも大きく変わります。
保証書は必ず受け取り、内容・有効期間・対象範囲をしっかり理解しておく
どんな場合に保証が適用されるのか、逆にどんな場合は対象外なのかなど、曖昧なままにせず、工事完了時に業者に質問しておくと安心です。
無料点検や定期メンテナンスのサービスがあるかどうかも要チェック
万が一の不具合や再発があった場合、すぐに相談できる体制がある業者なら、長期にわたる家の安心につながります。
施工業者の連絡先や、担当者名・窓口を分かりやすい場所に控えておく
例えば保証書と一緒にクリアファイルにまとめておいたり、スマホのメモアプリに記録しておくと「何かあったときすぐ相談できる」「家族みんなが連絡先を把握している」といった安心感につながります。
まとめ
防水工事の寿命をしっかり伸ばし、雨漏りや大規模修繕のリスクを回避するには、「こまめなメンテナンス」と「早期対応」が何より大切です。
万が一、不安や疑問を感じたら、そのまま放置せず、専門業者や防水のプロ集団「水防人」をぜひご活用ください。
【水防人】では、全国の信頼できる防水工事業者を無料でご紹介。ご相談から見積もりまで専門スタッフが丁寧にサポートしますので、
「どこに相談したらいいか分からない」「複数社の意見を聞いてみたい」といったお悩みも安心です。
住まいを長く快適に守るために、プロの力を上手に頼りながら、確かな防水メンテナンスを続けていきましょう。